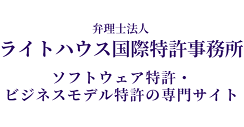特許法第29条の2の規定とは

1.特許法第29条の2の規定とは?
発明が特許を受けるためには、発明が新規性や進歩性を有することが求められますが、その他にもいくつかの要件を満たす必要があります。特許法第29条の2の規定もその1つです。特許法第29条の2は、「拡大先願」や「準公知」の規定とも言われます。
特許法第29条の2では、以下のように規定しています。
特許出願に係る発明が当該特許出願の日前の他の特許出願又は実用新案登録出願であつて当該特許出願後に第六十六条第三項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した特許公報(以下「特許掲載公報」という。)の発行若しくは出願公開又は実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第十四条第三項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した実用新案公報(以下「実用新案掲載公報」という。)の発行がされたものの願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面(第三十六条の二第二項の外国語書面出願にあつては、同条第一項の外国語書面)に記載された発明又は考案(その発明又は考案をした者が当該特許出願に係る発明の発明者と同一の者である場合におけるその発明又は考案を除く。)と同一であるときは、その発明については、前条第一項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。ただし、当該特許出願の時にその出願人と当該他の特許出願又は実用新案登録出願の出願人とが同一の者であるときは、この限りでない。
非常にわかりにくいですよね。簡単にすると、以下のようになります。
審査の対象となる出願を後願とします。そして、後願よりも先に出願されたものを先願とします。特許法第29条の2は、後願が、先願の出願の後で、先願の出願公開前に出願をしているような場合に適用されます。そして、後願の請求項にかかる発明が、先願の明細書に記載された場合は、特許を受けることができません。
先願が出願公開された後に、後願について特許出願されている場合は、後願が新規性を有していないことを理由に、後願は特許を受けることができません。ですが、後願が、先願の出願公開よりも前に、特許出願をしていた場合は、新規性の規定により、後願の特許性を否定することができません。ただ、このような後願は、何ら新しい技術を世の中に提供をするものではありません。
そこで、特許法第29条の2を設けることで、このような出願について、特許を受けることができない旨が規定されています。
このように、特許法第29条の2は、「公知」(特許法第29条第1項第1~3号)の規定に準ずる規定ですので、「準公知」とも呼ばれます。
このように、特許法第29条の2の規定は、先願の出願の後で、先願の出願公開よりも前に出願された後願が、特許を受けることができない旨を定めたものですが、例外もあります。
先願と後願の発明者が同一の場合は、特許法第29条の2の規定により、後願の特許性を否定されることはありません。発明者が複数の場合は、先願の発明者と、後願の発明者が完全に一致していることが求められます。
また、先願と後願の出願人が同一の場合も、特許法第29条の2の規定により、後願の特許性を否定されることはありません。出願人が複数の場合は、先願の出願人と、後願の出願人が完全に一致していることが求められます。
なお、この先願と後願の出願人が一致していることが求められるのは、後願の出願時のみです。
例えば、後願の出願時に、先願と後願の出願人が一致していて、その後、後願の出願人が変わって、先願と後願の出願人が一致しなくなっても、特許法第29条の2の規定により、後願の特許性が否定されることはありません。
上記のように、先願と後願の発明者、出願人のいずれかが一致していれば、特許法第29条の2の規定により後願の特許性が否定されることはありませんので、基本発明について出願をした後に、同一の企業が、その基本発明について出願公開されるまでに関連発明を出願しても、特許法第29条の2の規定により関連発明の出願の特許性が否定されることはありません。
ただし、これは日本だけの話であり、外国では必ずしも同じ取り扱いとなるわけではありません。
例えば、ヨーロッパ特許庁へ出願した場合、先願と後願の発明者が一致していたとしても、或いは、先願と後願の出願人が一致していたとしても、後願の請求項にかかる発明が、先願の明細書に記載されていれば、新規性を有しないとして、拒絶されます(ヨーロッパ特許の場合は、新規性を有しないものとして捉えられます)。
ですから、日本だけでなく、海外でも特許を取得することを考えるのであれば、このことを考慮したうえで、出願をしていく必要があります。より具体的には、先に出願する明細書において、後に出願をする可能性のある発明の具体的な内容について記載しないこと、が必要となります。
2.特許法第29条の2の判断手法と反論方法
次に、特許庁の審査における、特許法第29条の2の具体的な判断手法について、見ていきましょう。
まず、後願の請求項に係る発明を認定します。次に、先願の明細書、特許請求の範囲、図面に記載された発明を認定します。そして、後願の請求項にかかる発明と、先願の明細書、特許請求の範囲、図面に記載された発明(引用発明)とを対比します。
請求項にかかる発明の発明特定事項と、引用発明の発明特定事項とに相違がない場合は、請求項にかかる発明と引用発明は同一であると判断され、請求項にかかる発明は、特許法第29条の2の規定により特許を受けることができません。
このような拒絶理由通知を受けた場合、請求項にかかる発明と引用発明の認定について、審査官の認定が誤っている場合は、審査官の発明の認定に誤りがあることを意見書で説明します。発明についての審査官の認定が誤っていない場合は、請求項の記載を補正して対応することになります。
また、請求項にかかる発明の発明特定事項と、引用発明の発明特定事項とに相違がある場合であっても、それが課題解決のための具体化手段における微差である場合は、実質同一であると判断され、請求項にかかる発明は、特許を受けることができません。課題解決のための具体化手段における微差とは、周知技術、慣用技術の付加、削除、転換等であって、新たな効果を奏するものではないことを言います。
例えば、先願に「A手段とB手段とを備える装置」が記載されていたとします。そして、後願の請求項が「A手段とB手段とC手段とを備える装置」であったとします。後願の請求項は、先願に記載されていない「C手段」を備えていますので、特許法第29条の2の規定が適用されることはなさそうに思えます。
ですが、この「C手段」が周知技術である場合、後願の請求項にかかる発明は、先願に記載された発明に対して周知技術を付加したものとなります。周知技術を付加することで新たな効果を奏さないのであれば、先願に記載された発明と、後願の請求項にかかる発明は、実質的に同一である、と判断されます。つまり、特許法第29条の2の規定により、後願は特許を受けることができません。
このような拒絶理由が通知された場合の反論の方法としては、「C手段」が周知技術ではないことを証明するか、C手段により「新たな効果」を奏することを証明することがあげられます。ただし、「C手段」が周知技術でないことを証明するのは、なかなかに難しいと思われます。
ここで「新たな効果」ですが、周知技術であるC手段がもともと有している効果は、新たな効果とはなりません。A手段やB手段を備えている装置に、さらにC手段を付加した場合に、C手段がもともと有している効果以上の新しい効果が発揮されるような場合に「新たな効果」を有している、と言うことができます。つまり、A手段やB手段と、C手段との間に相乗効果が生まれないと、「新たな効果」を奏するとは言えませんので、ご注意ください。
<関連記事>
| 特許の知識にもどる |