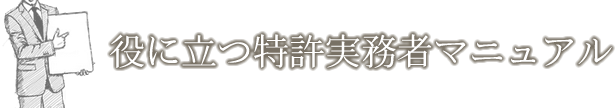こんにちは。田村良介です。
特許行政年次報告書って、ご存知でしょうか。
知的財産に関する統計情報をもとに、
知的財産制度を取り巻く現状、国内外の動向を
取りまとめたもので、
年に1回、特許庁より発行されています。
https://www.jpo.go.jp/shiryou/toukei/gyosenenji/index.html
例えば、出願数の推移や、特許査定数の推移などが
統計としてまとめられています。
この年次報告書によると、
特許査定率の推移は、以下のようになっています。
2011年 60.5%
2012年 66.8%
2013年 69.8%
2014年 69.3%
2015年 71.5%
2016年 75.8%
実は、ここ数年、特許査定率は、
急激にあがっているようです。
それと、もう一つ。
ファーストアクション期間の推移です。
2011年 25.9か月
2012年 20.1か月
2013年 14.1か月
2014年 9.6か月
2015年 9.5か月
2016年 9.5か月
ファーストアクション期間は、審査請求をしてから、
審査結果の最初の通知がされるまでの平均の期間です。
ファーストアクション期間は、
ここ数年、急激に短くなっています。
おそらくなのですが、
審査を迅速化させて、
ファーストアクション期間を短くした結果、
これまで、拒絶査定になっていたようなものでも、
特許として認められて、
特許査定率があがっているのではないかと思われます。
自社の出願が特許になりやすくなることは、
喜ばしいことですが、
その反面、
競合他社の出願も特許として認められやすく
なっているかもしれません。
|◆今日のポイント◆
└───────────────────
☆近年、特許査定率が大きく上昇している。
☆自社の出願が特許になりやすくなることは喜ばしいが、
その反面、
競合他社の出願も特許として認められやすく
なっているので、注意をする。
————————————————————————————–
■当メールマガジンについて
※当メールマガジンは、私個人の特許に対する考え方や
ノウハウをお伝えするものであり、ご紹介する内容の
すべてが絶対的に正しいとは、考えておりません。
予めご了承いただいたうえで、お読みください。
■メールマガジン「役に立つ特許実務者マニュアル」は
著作権により保護されています。
————————————————————————————–
こんにちは。田村良介です。
休日に家族で「ビール工場」の工場見学に
行ってきました。
ビールがどうやってつくられるのかにも
興味があったわけですが、
それよりも、ビールが飲めるかも?
という期待の方が、大きかったかもしれません。
工場見学の最後には、お待ちかね、
ビールの試飲が待っていました。
なんと、3種類のビールから好きなものを、
グラス3杯分まで飲んでも良い、とのこと。
お昼から、酔っ払ってしまいました。
ところで話はガラッと変わりますが、
インターネットで、
「間違った意味で使われている単語ランキング」
なるものを発見しました。
例えば、「ハッカー」。
広辞苑によると、
「コンピュータに精通し、熱中している人」。
それが転じて、
「コンピューターシステムに不法に侵入して
プログラムやデータを破壊する人」
になったようです。
間違った意味で使われている単語として、
その他にも「他力本願」、「破天荒」、
「なしくずし」などがあげられていました。
どうも、私は、その多くについて、
本来の意味を知らなかったようです。
仕事がら、日本語には自信があったわけですが、
実は、日本語力ないかも。。。あはは。。。
このように、一般に当然と思われていることでも、
実は誤っている、みたいなことは
あるかもしれませんね。
さて、本題です。
特許の業界では、
「権利範囲が広くなるように、より上位概念の
単語を用いて請求項を書きましょう」
ということが、よく言われます。
ただ、私が請求項を記載するときに、
単語を上位概念化することを意識しているか?
というと、あまり意識していないんですよね。
では、何を意識しているかというと、
『その発明の効果が得られる理由は何か?』
ということ。
発明の効果が得られる理由が分かれば、
『発明の本質的な要素が何か』が見えてきます。
その本質的な要素をもとに記載すれば、
用いる単語を上位概念化することを
特に意識しなくても、
自然とより上位概念の単語を用いて、
請求項を記載することができます。
上位概念化ありきではなく、
発明の本質的要素を捉えれば、
上位概念化もできますし、
可能な限り、広い請求項を
記載することができます。
一方、単語を上位概念化することだけを
意識していると、
発明の本質的要素を捉えることができずに、
結果として、権利範囲は狭くなるのではないかと。
もしかすると、
「上位概念化して請求項を記載する」は、
特許業界の「ハッカー」かもしれません。
|◆今日のポイント◆
└───────────────────
☆権利範囲の広い請求項を書くポイントは、
単語を上位概念化することではなく、
『発明の本質的要素は何か?』
を考えること。
————————————————————————————–
■当メールマガジンについて
※当メールマガジンは、私個人の特許に対する考え方や
ノウハウをお伝えするものであり、ご紹介する内容の
すべてが絶対的に正しいとは、考えておりません。
予めご了承いただいたうえで、お読みください。
■メールマガジン「役に立つ特許実務者マニュアル」は
著作権により保護されています。
————————————————————————————–
こんにちは。田村良介です。
特許や商標など、知的財産に関する仕事は、
一つのミスが大きな問題につながることがあります。
例えば、特許出願をしてから3年以内に
出願審査請求をしなければ、
特許庁で審査されることはなくなりますから、
特許を取得することができなくなります。
出願審査請求をする際に、
出願番号を誤って記載して特許庁に提出すると、
大変なことになります。
こういった重大なミスを防ぐために、
特許事務所ではダブルチェックなどの
対策を行っています。
ところで、
皆さんもお気付きのように、
仕事をしていてミスの少ない人と多い人がいます。
ミスが多いのは、本人の注意不足によるところも
多いのですが、
人によってミスが多くなる理由は、
これだけではないと思っています。
というのも、
ミスが少ない人は、
『ミスが発生しにくい手順や方法』
で仕事を進めていますし、
ミスが多い人は、
『ミスが発生しやすい手順や方法』
で仕事を進めています。
要は、注意力だけに頼るから
ミスが起こるのであって、
ミスが発生しにくいように、手順や方法が
改善されていないのが、原因だったりします。
例えば、ちょっとしたことですが、
私は、明細書、意見書、お客さまに提出する
コメントなど、文章を作成した場合は、
必ず印刷をして読み直すように徹底をしています。
ディスプレイを見ながら確認をしていても、
どうしても気が付かないことがあります。
このちょっとしたことをするだけで、
誤字脱字、
冗長になっている文章、
読み手にとって理解しづらくなっている文章、
読み手が誤った解釈をする可能性がある文章などを、
かなりの確率で、発見することができます。
おかげさまで、田村さんの文章は読みやすい、
ということを、よく言っていただけます。
話は少しそれましたが、
言いたかったことは、
ミスが発生しにくいように、
手順や方法を工夫することで、
ミスは防げる、ということです。
|◆今日のポイント◆
└───────────────────
☆注意力だけに頼るのではなく、
手順、方法を工夫することで、ミスは防げる。
————————————————————————————–
■当メールマガジンについて
※当メールマガジンは、私個人の特許に対する考え方や
ノウハウをお伝えするものであり、ご紹介する内容の
すべてが絶対的に正しいとは、考えておりません。
予めご了承いただいたうえで、お読みください。
■メールマガジン「役に立つ特許実務者マニュアル」は
著作権により保護されています。
————————————————————————————–
こんにちは。田村良介です。
皆さん、耶律楚材(やりつそざい)
という人物をご存知でしょうか。
世界史が好きな方なら、ご存知かもしれません。
モンゴル帝国を作ったチンギス・カーンの側近が、
耶律楚材です。
この耶律楚材の名言に、
「一利を興すは一害を除くに如かず」
というものがあります。
意味は、
「1つの利益のあることを始めるよりも
1つの害を取り除くことの方が良い」
というもの。
例えば、
健康について当てはめてみると、
青汁を飲むことが一利であるとするなら、
深夜にラーメンを食べることが一害にあたります。
つまり、深夜にラーメンを食べることをやめる方が、
青汁を飲むことよりも、健康にとって有効だということ。
良い食習慣を一つ作るよりも、
悪い食習慣をなくす方が、難しいのですが、
その方が、より健康にも効果的なのでしょうね。
ところで、
「一利を興すは一害を除くに如かず」は、
特許の世界でも言えることかもしれません。
特許出願をして自社の製品を保護する、
ということが、一利であるとすれば、
自社の製品が他社の特許権を侵害することは、
一害なわけです。
他社の特許権を侵害すると、
その製品の製造・販売ができなくなることもありますから。
そう考えると、
他社の特許を侵害するリスクを排除する、
自社にとって問題となる他社特許をゼロにする、
という活動が、
場合によっては、特許出願をするよりも重要
と言えるのかもしれませんね。
そうすると、次に、
他社の特許権を侵害する、
という一害を除くには?
という問いが出てきます。
例えば、他社特許をつぶしてしまう。
無効審判や特許異議申立てをするだけでなく、
調査をして無効にできそうな資料を集めておく、
ということだけでも良いかも知れません。
また、自社特許と他社特許とをクロスライセンスをして、
他社特許の侵害とならない状態にする、
というのも1つ。
製品の設計を変更して、
他社特許にひっかからないようにする、
というのも選択肢としてあります。
|◆今日のポイント◆
└───────────────────
☆一利を興すは一害を除くに如かず。
☆他社特許の侵害を防止するための活動は、
最も重要な活動の1つ。
————————————————————————————–
■当メールマガジンについて
※当メールマガジンは、私個人の特許に対する考え方や
ノウハウをお伝えするものであり、ご紹介する内容の
すべてが絶対的に正しいとは、考えておりません。
予めご了承いただいたうえで、お読みください。
■メールマガジン「役に立つ特許実務者マニュアル」は
著作権により保護されています。
————————————————————————————–
こんにちは。田村良介です。
永禄3年5月19日。
2万5千もの大軍で尾張に侵攻した今川義元。
一方、織田信長は、明け方に清州城を出発。
熱田神宮で戦勝祈願を行った後、
善照寺砦で2千~3千の軍勢を整えます。
2千の兵で善照寺砦から出撃し、雨の中、兵を進め、
桶狭間にいる今川義元に奇襲をかけます。
今川義元は、織田家臣の毛利良勝に打ち取られ、
織田家は、この戦いで大勝利をおさめます。
桶狭間の戦い、
教科書にも出てくる、非常に有名な戦いです。
今川勢の2万5千のうち、
桶狭間で今川義元を守る兵は5千程度だったそうです。
この戦いで、織田勢が勝利をおさめた理由としては、
今川勢の油断、天候、信長の徹底した情報管理などが
あるのだとは思うのですが、
兵数の差による不利を、局所的に小さくすることが
できたことも、1つの理由ではないかと思います。
ランチェスター法則を、
経営に応用したランチェスター戦略でも、
弱者が強者に勝つための原則として、
「一点集中主義」があげられています。
限られたリソースを、
特定の地域、顧客層、用途などにしぼることで、
市場で優位性を発揮することができます。
この「一点集中主義」は、
特許の分野にも応用できるのではないかと。
開発のリソースを一点集中するのもそうですが、
特許を取得するための予算や人員も、
特定の製品や特定の技術に、より優先的に配分する。
(すでに、そのように実践されている企業さんは、
多々あるかと思いますが)
そうすることで、
競合他社に対して、より競争優位になり、
その優位性を持続させることができるように思います。
|◆今日のポイント◆
└───────────────────
☆ランチェスター戦略では、
弱者が強者に勝つための原則として、
「一点集中主義」があげられている。
☆特許の分野でも、
特定の製品や特定の技術に、
より優先的にリソースを配分することで、
競争優位性を高めることができる。
————————————————————————————–
■当メールマガジンについて
※当メールマガジンは、私個人の特許に対する考え方や
ノウハウをお伝えするものであり、ご紹介する内容の
すべてが絶対的に正しいとは、考えておりません。
予めご了承いただいたうえで、お読みください。
■メールマガジン「役に立つ特許実務者マニュアル」は
著作権により保護されています。
————————————————————————————–