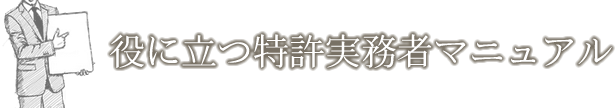こんにちは。田村良介です。
■これまで、何度も、セミナー講師として、
新規性・進歩性の拒絶理由通知への対応方法について、
お話をさせていただきました。
私自身、拒絶理由通知への対応には、
かなりのこだわりがあります。
なぜ、拒絶理由通知への対応にこだわるのか?
いくらしっかりとした明細書を書いても、
拒絶理由通知への対応が悪ければ、
特許にはなりません。
また、取りたかった範囲で、
特許をとれるか否かも、
拒絶理由通知への対応の良し悪しで決まってきます。
■フランスの哲学者 ブレーズ・パスカルの名言。
「力なき正義は無能である」
少し大げさでしょうか?
でも、いくら素晴らしい発明でも、
意見書でそのことを十分に伝えられなければ、
特許が認められない場合もあるわけです。
■日々、努力をして研究、開発を進め、
他社品とは差別化された発明品を開発します。
その差別化された部分を、他社に真似されないように、
特許出願をします。
特許庁での審査の結果、
おそらく審査請求をしたもののうち8~9割は、
拒絶理由が通知されます。
もし、特許を取得できなければ、
他社が類似商品の販売を開始するかもしれません。
仮に、特許を取得できたとしても、
権利範囲が狭いと、
他社が容易に特許を回避して、
類似の商品を開発するかもしれません。
■私が拒絶理由通知にこだわる理由。
それは、
拒絶理由通知への対応の良し悪しで、
取得できる権利範囲が決まり、
その後の事業の競争力にも影響を与えるからなのです。
有効な特許を取得し、
差別化された商品を市場に投入しつづけることができれば、
シェアを奪われるリスクも少なくなりますし、
価格競争にも巻き込まれにくくなります。
もちろん、特許が万能なわけではありません。
特許を取得したとしても、競合する製品はでてくるでしょう。
ただ、可能なかぎり、広い範囲で権利化をすることで、
少しでも良いポジションで事業を進めることができるのではないか、
と考えております。
————————————————————————————–
■当メールマガジンについて
※当メールマガジンは、私個人の特許に対する考え方や
ノウハウをお伝えするものであり、ご紹介する内容の
すべてが絶対的に正しいとは、考えておりません。
予めご了承いただいたうえで、お読みください。
■メールマガジン「役に立つ特許実務者マニュアル」は
著作権により保護されています。
————————————————————————————–
こんにちは。田村良介です。
最近は、審査請求をした後、
特許庁からのファーストアクションが
届くまでの期間が大幅に短くなりました。
特許出願と同時に審査請求をすれば、
2年以内に特許になるかどうかが分かります。
そうやって、多くの出願にたずさわっていて、
いつも感じるのですが、
特許出願をする時は、
『進歩性が認められない可能性が高い』、
『特許にするのが厳しいかも』、
と思っていたものでも、
明細書作成の際に準備をし、
拒絶理由通知の際にしっかりと対応すれば、
特許は認められるものだなぁ、と。
そして、そのような出願こそ、
他社に対しての牽制効果も高いことが多いと。
こういう経験をするにつれ、
『出願をする前に、
「進歩性がないだろう」という理由で、
特許出願をあきらめるのは、もったいない』
と感じます。
特許が認められる可能性は高くなくても、
特許が認められた場合に、他社に対する牽制効果が
大きなものとなる可能性が高いのであれば、
チャレンジする、というのも選択肢としてあるはず。
極端ではありますが、
新規性さえあれば、あとは、どうやって進歩性を
主張するのかを考える、
というスタンスの方が良いのではないかと、
思っています。
|◆今日のポイント◆
└───────────────────
☆「進歩性がないだろう」という理由で、
特許出願をあきらめるのは、もったいない
☆進歩性が弱そうなものでも、
明細書作成の際に準備をし、
拒絶理由通知の際にしっかりと対応すれば、
特許が認められる可能性は十分にある
————————————————————————————–
■当メールマガジンについて
※当メールマガジンは、私個人の特許に対する考え方や
ノウハウをお伝えするものであり、ご紹介する内容の
すべてが絶対的に正しいとは、考えておりません。
予めご了承いただいたうえで、お読みください。
■メールマガジン「役に立つ特許実務者マニュアル」は
著作権により保護されています。
————————————————————————————–
こんにちは。田村良介です。
先日の10月1日で、特許事務所を開業して、
10年が経過しました。
これも、お仕事のご依頼をいただけるお客様や、
日頃から応援して下さる皆様のおかげです。
ありがとうございます。
今後とも、よろしくお願い申し上げます。
さて、大変ありがたいことに、
これまで何十回と、セミナーでお話をする
機会をいただきました。
「拒絶理由通知への対応」というテーマでも、
何度もお話をさせていただいています。
実は、「拒絶理由通知への対応セミナー」で、
いつもお話をしていることがあります。
それは、
『特許がとれる内容で、特許をとるのではなく、
特許をとりたい内容で、特許をとりましょう。』
というもの。
拒絶理由通知の内容を読むと、ついつい、
『審査官の主張はもっとも。
反論するのは難しい・・・』
と感じてしまうことがあります。
そうすると、審査官との真っ向勝負はさけ、
確実に特許をとれるように、請求項を補正して、、、
となりがちです。
ですが、特許が確実にとれそうな内容で、
仮に特許が認められたとしても、
それが他社に対しての牽制にならなければ、
特許権を取得する意味はないわけで。
そこで、セミナーでは、
『特許をとりたい内容、他社に対しての牽制になる内容で、
特許が認められるためには、どうすればいいか?』
という視点で考えて下さい、
ということをお願いしているわけです。
ただ、特許をとりたい内容で審査官に特許を認めてもらう、
というのは、そんなに簡単ではなかったりします。
そのために、拒絶理由通知へ対応するための高いスキルが
必要となりますし、
セミナーでは、そのための考え方やノウハウをお伝えしています。
|◆今日のポイント◆
└───────────────────
☆特許がとれる内容で、特許をとるのではなく、
特許をとりたい内容で、特許をとる。
————————————————————————————–
■当メールマガジンについて
※当メールマガジンは、私個人の特許に対する考え方や
ノウハウをお伝えするものであり、ご紹介する内容の
すべてが絶対的に正しいとは、考えておりません。
予めご了承いただいたうえで、お読みください。
■メールマガジン「役に立つ特許実務者マニュアル」は
著作権により保護されています。
————————————————————————————–
こんにちは。田村良介です。
このメールマガジンも、
途中で期間が空いたりもしながら(汗)、
150回目の発行になります。
こうやって、メールマガジンを発行することで、
最も勉強になっているのは、実は、私だったりします。
考えていることを文章にしようとすると、
うまく書けないことがあります。
途中で、キーボードをたたく指が止まります。
「あれっ? なんでだろう?」
実は、理解しているようで、
理解できていない部分があるから、
突き詰めて考えているようで、
突き詰めて考えられていない部分があるから、
手が止まります。
そこではじめて、自分の理解が十分でないこと
に気が付きます。
気が付けば、あとは、調べ、考え、
それを理解するための努力をします。
もうひとつ。
文章を書いていると、
自分の考えが深まっていくことがあります。
自分の書いた文章をきっかけに、
新しい気付きが生まれてくる、
という感じでしょうか。
セミナー講師をさせていただくときも、
そうなのですが、
何かを発信することで、
自分の考えを深めるきっかけとなります。
|◆今日のポイント◆
└───────────────────
☆何かを発信するために文章を書くことで、
・自分が理解できていないことに気が付く、
・自分の考えを深めることができる、
というメリットがある。
————————————————————————————–
■当メールマガジンについて
※当メールマガジンは、私個人の特許に対する考え方や
ノウハウをお伝えするものであり、ご紹介する内容の
すべてが絶対的に正しいとは、考えておりません。
予めご了承いただいたうえで、お読みください。
■メールマガジン「役に立つ特許実務者マニュアル」は
著作権により保護されています。
————————————————————————————–
こんにちは。田村良介です。
明細書を書くことに慣れていない段階では、
発明の内容を、どこまで具体的に書けば良いのか、
迷うことがあるかと思います。
こんなとき、
明細書に何を書くのかの基準をもっていると、
大きく悩むことなく、安心して、
明細書の作成を進めて行くことができます。
それでは、明細書に何を書くかですが、
以下を意識していただくと良いのではないかと。
・実施可能要件・サポート要件などの
記載要件を満たすために必要なことを記載する
・将来、補正をする際の補正の根拠となり得る
ことを記載する
まず、1つ目。
簡単に言うと、
明細書を見た人が、
「明細書の記載+技術常識をもとに、
発明を実施できる程度に記載する」
必要があります。
その発明の内容を知らない人が、
明細書の記載とその分野の技術的な常識の
両方を考慮に入れると、発明が実施できる、
と言えるまで、
具体的に発明の内容を説明していきます。
例えば、
明細書の記載とその分野の技術的な常識をもとに、
発明品を製造できるように記載します。
次に、2つ目。
将来、補正をしたいと思ったときに、
記載があればいいなぁ、
と思うものを記載します。
つまり、補正の根拠となりそうな事項を
記載します。
補正の根拠となりそうな事項とは、
「発明の効果に影響を与えるだろう要素」
と言っても良いかもしれません。
例えば、発明の効果が、
成型品の強度であったとします。
そうすると、
成型品の強度に影響を与えそうな要素
(例えば、成型品の組成の比)が、
補正の根拠となり得るので、記載しておいたほうが良い、
ということになります。
例えば、運動器具に関する発明であれば、
運動の効果の高さに影響を与えそうな要素、
運動時の安全性に影響を与えそうな要素などを
明細書に記載しておく、ということになります。
|◆今日のポイント◆
└───────────────────
☆明細書には何を記載するのか?
・実施可能要件・サポート要件などの
記載要件を満たすために必要なことを記載する
・将来、補正をする際の補正の根拠となり得る
ことを記載する
————————————————————————————–
■当メールマガジンについて
※当メールマガジンは、私個人の特許に対する考え方や
ノウハウをお伝えするものであり、ご紹介する内容の
すべてが絶対的に正しいとは、考えておりません。
予めご了承いただいたうえで、お読みください。
■メールマガジン「役に立つ特許実務者マニュアル」は
著作権により保護されています。
————————————————————————————–