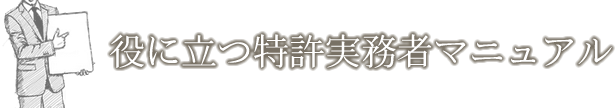こんにちは。田村良介です。
高橋利幸さんという方をご存知でしょうか。
高橋名人、と言った方が、ピンとくる方もいらっしゃるかもしれません。
高橋名人は、
ファミリコンピュータ(いわゆるファミコン)の全盛時代に、
ゲームの名人として、当時の子供たちに絶大な人気のあった人です。
私もゲーム好きな子供でしたので、高橋名人のファンの一人でした。
高橋名人の著書の中に、
『ボタンを1秒間に16回連射するには、握力や腕の力が必要』
と書いてあったので、握力を鍛えたり、腕立てをしたり・・・
ゲームを上手になるために、一生懸命になっている小学生の息子を見て、
母親は冷たい視線をそそいでいました・・・。
高橋名人の著書の中で、
もう30年以上経っているはずなのに、今も覚えていることがあります。
それは、、、、
『 ゲームを上手になりたければ、
1面をクリアーできても、すぐに2面、3面へと進むのでなく、
1面を100%の確率でクリアーできるまで、何度も1面をやり続けるといい。
1面には、そのゲームの基本的な要素の全てが含まれているから。』
というものでした。
プロ野球選手も、
いつもピッチャーをつけてバッティングをしているわけではなく、素振りもします。
松井秀喜さんが、長嶋茂雄さんの指導のもと、繰り返し素振りを練習したというのは、
有名な話です。
つまり、
物事に習熟するには、基本の徹底が重要、
ということでは、ないかと思います。
ところで、我々、特許の実務に携わる人にとっての基本とは何か?
と考えたとき、
特許庁の『特許・実用新案審査基準』の理解があげられると思います。
審査基準は、教科書みたいなものかもしれません。
でも、意外と、審査基準を読み込んでいる方は少ないのではないか、
とも思っています。
うちの事務所では、週1で、この審査基準の読み合わせをしています。
週1であっても、1年、2年と続けていくことで、
何度も審査基準と向き合うことになります。
私もこの仕事をはじめて10年以上経ちますが、
それでも、いまだに審査基準から新しい発見があります。
私が、この業界に入ったばかりのころは、
毎日、通勤電車の中で、審査基準とにらめっこをしていました。
そうやって、審査基準を読み込んでいると、仕事をしている最中に、
『審査基準のあのあたりに、今の案件と似たような状況の事例があげられていたかも』
といったことが起こってきます。
こうなると、しめたもので、
審査基準が活きた知識となってきますし、仕事のクオリティも上がってきます。
|◆今日のポイント◆
└───────────────────
☆物事に習熟するには、基本の徹底が重要。
☆特許の実務に携わる人にとって、
『特許・実用新案審査基準』の理解は、仕事をするうえでの足腰をつくるもの。
————————————————————————————–
■当メールマガジンについて
※当メールマガジンは、私個人の特許に対する考え方や
ノウハウをお伝えするものであり、ご紹介する内容の
すべてが絶対的に正しいとは、考えておりません。
予めご了承いただいたうえで、お読みください。
■メールマガジン「役に立つ特許実務者マニュアル」は
著作権により保護されています。
————————————————————————————–
こんにちは。田村良介です。
トヨタ自動車の元副社長をされていた大野耐一さんの
『トヨタ生産方式 脱規模の経営をめざして』という書籍があります。
大野耐一さんは、トヨタ生産方式の生みの親とも呼べる方だそうです。
この書籍の中でも紹介されていますが、
大野耐一さんが提唱したと言われる考え方として、
「なぜを5回繰り返す」というものがあります。
例えば、
何らかのトラブルが発生したときに、
「なぜを5回繰り返す」ことで、トラブルの真の原因を探ることができる、
というものです。
なぜを5回繰り返さないと、すぐに思いつく答えを結論としてしまい、
表面に見える状況だけについて、対応することになります。
結局、根本的な解決はできず、
何度も問題が繰り返されることになります。
ところで、うちには、4歳の息子がいますが、
母親が叱ると言うことを聞くのに、私が叱ると、私に立ち向かってきます・・・。
『なぜ、私が叱ると、立ち向かってくるのか?』
↓
私を友達だと思っているから。
↓
『なぜ、友達だと思っているのか?』
↓
父親としての威厳を示すことができていないから。
↓
『なぜ、威厳を示すことができていないのか?』
↓
息子と一緒になって、バカな遊びをしているから。
といったように、真の原因を探りあてることができます。
それはさておき、
「なぜを5回繰り返す」ことで、
ものごとの本質を探りあてることができるのだと思います。
例えば、発明の捉え方についても、
なぜを繰り返すことで、発明の本質を探りあてることができます。
『なぜ、断面が六角形の鉛筆は、
断面が円形の鉛筆よりも転がりにくいのか?』
↓
断面が多角形だから
↓
『断面が多角形だとなぜ転がりにくいのか?』
↓
断面の中心から外周までの距離が異なるから
↓
『なぜ、中心から外周までの距離が異なると、
転がりにくくなるのか?』
↓
転がる際に、重心の高さが変わって、
水平方向に移動する運動エネルギーが、
垂直方向に移動する運動エネルギーに変換されて
消費されるから。
断面が多角形だから、という結論でとまっていた場合、
請求項は、「断面が多角形の鉛筆。」
となります。
断面の中心から外周までの距離が異なるから、という結論の場合、
請求項が、
「中心から外周までの距離が異なる形状の断面を有する、鉛筆。」
といったような感じになります。
この場合、断面が多角形以外のもの、
例えば、断面が楕円形のものも含まれます。
楕円形の鉛筆について、商業的に需要があるかどうかは別として、
『なぜ?』『なぜ?』と転がりにくい原因を追求することで、
発明の本質に近づきますし、権利範囲もより広がります。
六角形の鉛筆が転がりにくい理由として、
転がる際に重心の高さが変わる、という結論にいたった場合には、
請求項が・・・。
すみません。
大変そうなので、割愛させてください(笑)。
このように、「なぜを5回繰り返す」ことで、
発明の本質的な要素を探りあてることができるのではないか
と思います。
|◆今日のポイント◆
└───────────────────
☆発明を捉える際には、「なぜを繰り返す」。
☆「なぜを繰り返す」ことで、
発明の本質的な要素を捉えた請求項を
記載することができるのではないか。
☆結果として、より広い権利範囲の請求項を
記載することができる。
————————————————————————
■当メールマガジンについて
※当メールマガジンは、私個人の特許に対する考え方や
ノウハウをお伝えするものであり、ご紹介する内容の
すべてが絶対的に正しいとは、考えておりません。
予めご了承いただいたうえで、お読みください。
■メールマガジン「役に立つ特許実務者マニュアル」は
著作権により保護されています。
————————————————————————
こんにちは。田村良介です。
先日、おもしろいお店を発見しました。
キャンディをラッピングしてブーケのようにしたキャンディブーケの専門店です。
店内はキャンディブーケで埋まっていて、見ているだけで、楽しい気分になってきます。
ブーケに使われているキャンディ、チョコレート、ラムネなどは、数十個ですが、
これがブーケになると、すごく華やかになります。
誕生日やお祝いごとなど、ちょっとしたプレゼントなどに、最適だと思います。
このキャンディブーケ、
原価はそれほどかかっていないのではないかと思うのですが、
価格は数千円。
キャンディ+ブーケ
という発想で、新しい価値を生み出した、すばらしい商品ではないかと思います。
この新しい発想について、特許を取得することはできるでしょうか。
さすがに、
キャンディ+ブーケ
というコンセプトだけで、特許性が認められるのは、難しいかもしれませんが、
キャンディをラッピングするための何らかの工夫が、もしあるようであれば、
その工夫で、特許を取得することが考えられます。
大きな概念で特許を取得できなくても、
その概念を実現するにあたっての工夫で特許を取得することができれば、
仮に、他社が同じようなことを始めたとしても、優位性を保つことができます。
同じことが、ビジネスモデル関連のアイデアでも言えます。
例えば、ピザの宅配ビジネスで、
注文してから30分以内に届けなければ、ピザを無料にする、
ことを考え付いたとします。
ビジネスモデルそのものは、特許の対象とはされていません。
ただし、このビジネスモデルを実現するために工夫できることは、
たくさんあるのではないか、と思います。
ピザをはやく焼き上げるために、生地、ピザの形状、釜などを工夫したり、
ピザを効率的に配達するために、
どの配達先に、どの順番で配達するかを計算するシステムを開発したり・・・。
ビジネスアイデアそのものは特許になりませんが、
ビジネスアイデアを実現する際の工夫であれば、特許の対象となります。
こうした工夫で特許を取得することができれば、
他社が同じようなビジネスは始めたとしても、自社の優位性を保つことができます。
|◆今日のポイント◆
└───────────────────
☆アイデアそのものが特許の対象ではなくても、
そのアイデアを実現する際の工夫であれば、特許の対象となる。
☆アイデアを実現する際の工夫について、特許を取得することで、
自社の優位性を保つことができる。
————————————————————————
■当メールマガジンについて
※当メールマガジンは、私個人の特許に対する考え方や
ノウハウをお伝えするものであり、ご紹介する内容の
すべてが絶対的に正しいとは、考えておりません。
予めご了承いただいたうえで、お読みください。
■メールマガジン「役に立つ特許実務者マニュアル」は
著作権により保護されています。
————————————————————————
こんにちは。田村良介です。
以前、読んだ本にこんなことが書いてありました。
ある島にたどり着いた、2人の携帯電話のセールスマンがいました。
一人は
『ここでは誰も携帯電話を使っていない。飛行機ですぐに帰る。』
と、本国に連絡をいれました。
もう一人は
『ここでは誰も携帯電話を使っていない。すぐに携帯電話を5万台、送ってほしい』
と、本国に連絡をいれました。
おもしろいもので、同じ出来事でも、人によって、解釈は大きく異なります。
前者は、売上をあげることができませんが、
後者は、すばらしい営業成績をあげることができたかもしれません。
この2人の職業はセールスマンですから、
後者の方が、セールスマンとして適切な解釈をしているのでしょうね。
出来事をどのように解釈するかは、その人次第ですが、
できるだけ、自分にとってプラスになるような解釈をしていきたい、
この話を読んだときに、
そんなことを思ったのを覚えています。
振り返ってみると、
特許の世界でも、同じようなことがあります。
特許要件の1つである進歩性についてですが、
進歩性を有しているかどうかの一つの判断基準として、
先行技術と比べた有利な効果があるか、
というものがあります。
例えば、普通に考えると有利な効果がない、
と思えるような技術について、考えてみます。
従来品よりも強度がない素材は、
『強度』という点では劣っています。
ですが、もしかすると、
『柔軟性』という点では優れているかもしれません。
従来品よりも透明性がないフィルムは、
『透明性』という点では劣っているかもしれません。
ですが、もしかすると、
『隠ぺい性』という点では優れているかもしれません。
見方を変えることで、効果がないと思われるものでも、
効果を見出すことができることがあります。
では、従来品よりもコストダウンしたもので、
従来品と同等の性能を有する製品は、どうでしょうか。
コストダウンは技術的な効果ではありませんので、
コストダウンしたことを正面から主張しても、
進歩性の主張としては弱いでしょう。
ただ、見方を変えて、
従来はコストダウン品では必要な性能が得られなかった
↓
発明によりコストダウン品でも、
従来の高級品と同等の性能を得ることができた
ということであれば、
従来の性能の悪いコストダウン品と比べて、
技術的に優れたものである、
ということもできます。
出来事は解釈しだい、
発明も解釈しだい、
ということかもしれません。
|◆今日のポイント◆
└───────────────────
☆一見、すぐれた効果を有さないように思えるものでも、
解釈次第では、発明の効果を見出すことができる。
————————————————————————
■当メールマガジンについて
※当メールマガジンは、私個人の特許に対する考え方や
ノウハウをお伝えするものであり、ご紹介する内容の
すべてが絶対的に正しいとは、考えておりません。
予めご了承いただいたうえで、お読みください。
■メールマガジン「役に立つ特許実務者マニュアル」は
著作権により保護されています。
————————————————————————
こんにちは。田村良介です。
先週末にオフィスの移転作業を行いまして、
本日から新しいオフィスで業務です。
これまでより広いオフィスになり、
今はまだ、広々としていますが、
数年後には、ここも手狭になってきた、
と思えるように、頑張っていきたいと思います。
さて、「7つの習慣」という書籍をご存知でしょうか。
日本国内で130万部以上、全世界で2000万部以上を
売り上げたベストセラーです。
いわゆる自己啓発書なのですが、
個人、家庭、仕事などの人生すべての側面で
活用できる、7つの習慣を紹介するものです。
7つの習慣は、以下のようなものです。
第一の習慣 主体性を発揮する
第二の習慣 目的を持って始める
第三の習慣 重要事項を優先する
第四の習慣 Win-Winを考える
第五の習慣 理解してから理解される
第六の習慣 相乗効果を発揮する
第七の習慣 刃を砥ぐ
仕事上で「Win-Win」という言葉が
使われることがよくありますが、
この「7つの習慣」で広まったものではないかと。
私が社会人になりたての頃に、
仕事も、上司との関係もうまくいかず、
悩んでいた時期があったのですが、
その時期に、この本を読んで、
私自身、かなりの影響を受けた本でもあります。
ところで、
第五の習慣の「理解してから理解される」ですが、
人間関係を改善するための習慣として
あげられたものです。
相手のことを理解しようとせずに、
自分の主張をするだけでは、
相手に自分のことを理解してもらうこともできません。
相手のことを理解するからこそ、
自分のことを理解してもらえる土壌ができます。
私自身ができているとは、とてもとても言えませんが、
そうありたいと思っています。
なぜ、第五の習慣についてご紹介したのかというと
この習慣、特許の仕事にもあてはまるんです。
拒絶理由通知がだされたとき、
「審査官が何かおかしなことを言ってるなぁ」
と感じることがあります。
重要なのは、
審査官が何かを誤解していると感じたときに、
なぜ審査官が誤解しているか、
その理由を自分が理解できているか?
ということ。
審査官が誤解していると思いきや、
審査官の指摘が妥当であることに
気付いていないだけかもしれません。
うちの事務所の皆さんにも、
このことは、口酸っぱく言っています。
「審査官の言っていることがおかしいと思ったら、
自分の理解が間違っているのでは?」
と、自分自身の理解を疑うべきだと。
審査官の指摘の真意を理解せずに、
こちらの主張だけをしても、
的外れな反論となりますから、
当然、審査官を説得することはできません。
まずは、審査官の指摘の真意を理解すること。
そのためには、拒絶理由通知を
何度も繰り返し読むと良いかもしれません。
審査官の真意を理解することができれば、
拒絶理由通知への検討は、
7~8割、終了したも同然です。
あとは、その対応策を考えるだけです。
審査官を理解するからこそ、
こちらの主張も理解されます。
|◆今日のポイント◆
└───────────────────
☆審査官が何か誤解していると感じたときは、
自分が理解できていないだけかもしれない。
☆審査官の真意を理解するからこそ、
こちらの適切な主張ができるし、
審査官にも理解される。
————————————————————————
■当メールマガジンについて
※当メールマガジンは、私個人の特許に対する考え方や
ノウハウをお伝えするものであり、ご紹介する内容の
すべてが絶対的に正しいとは、考えておりません。
予めご了承いただいたうえで、お読みください。
■メールマガジン「役に立つ特許実務者マニュアル」は
著作権により保護されています。
————————————————————————